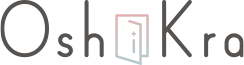本当に大切なのは“英語力”より“日本語力”~ミュージカル「訳詞」のお仕事 ー高橋 亜子さん(後編)ー【連載】推し事現場のあの仕事 #003
公開日 2021.12.03
わたしたちの“推し”が輝いている劇場やライブ会場となどの”現場”。そこではふだんスポットライトを浴びることが少ない、多くの人々によって作品が作られています。本連載では、現場の裏側から作品を支える様々なクリエイターたちに焦点を当て、現場でのモロモロや創作過程のエピソードなど、さまざまな“お仕事トーク”を深掘りしていきます。
第3回目のゲストは、ミュージカル『ビリー・エリオット』『デスノート THE MUSICAL』『パレード』など、さまざまな作品の訳詞や翻訳を手掛け、新作オリジナルミュージカル『フィスト・オブ・ノーススター~北斗の拳~』では脚本と作詞を担う高橋亜子(たかはし あこ)さん。
インタビュー後編ではご自身の意外な経歴や、訳詞をする上で必要な“力”についてうかがいました。(編集部)

高橋 亜子さん
前編はこちら▼
舞台芸術の仕事に就こうと飛び込んだ俳優養成所
――「訳詞」のお仕事をしている方に対して“英語一筋で頑張ってきた”みたいなイメージを持つ人も多いと思います。でも、高橋さんはちょっと違うんですよね。
高橋 私は元々内気なところがあり、喋ることで自己表現ができなかったんです。だけど胸の中に“思い”がないわけではないので、どうしたらその“思い”を人に伝えられるのか、ずっと考えているような学生時代を送っていました。
――心の内を語るより文章にする方が得意だった。
高橋 文章なら自分の感情を表現することができました。他にも絵を描いたり、音楽をやってみたりする中でミュージカルに出会って、これはすごいな!と。
――衝撃を受けた作品って覚えてます?
高橋 宝塚歌劇団が上演した『ME AND MY GIRL』です。
――その衝撃を胸に、ミュージカル劇団の俳優養成所に進まれます。
高橋 作曲家のいずみたくさんが創設した「イッツフォーリーズ」の養成所に通いました。これもちょっとおかしな話ですけど(笑)、当時も俳優になりたい!って強い意志があったわけじゃないんです。舞台美術にも興味がありましたし、照明プランナーもやってみたいし、小道具を作るのも大好きで、とにかく舞台芸術に関わる仕事をしたいと強く思っていました。あの頃はその入り口が俳優養成所以外に見つけられなくて。
――養成所時代はいかがでしたか。
高橋 2年間、とても楽しかったです。特に歌やダンスを習っていたわけでもなく入ったので、全部一からやりました。大変でしたが、ミュージカルの楽曲をたくさん知ることができましたし、さまざまなダンスも教えてもらえて、良い先生や良い仲間にも出会えました。

――2年の養成期間を終えて、劇団員としての活動が始まります。
高橋 その後は3年くらい、舞台に出てました。おもにアンサンブルとして地方の公演やお子さん向けの作品にも関わっていましたね。それである時、劇団の本公演でプリンシパル(=役名があり、重要な役割を担うキャラクター)にキャスティングしてもらって、出演していたのですが、そこで「あれ、違う……私、これじゃない」って。
――えっ、プリンシパルまで行ったところで……なぜ?
高橋 舞台の上で全然自由じゃなかったんですよ。いわゆるダメ出し的なことで上の人から否定されて、どうしたらいいのかわからなくなってしまって。いつの間にかお客さんに向けて芝居をする、作品を届ける……ではなく、内部の人に認められることが目的になってしまっていた自分に気づいたんです。それで、初プリンシパルの公演の千秋楽のカーテンコールで「これで終わり。私はもう舞台には立たない」って決めました。
――またスパっときましたね。
高橋 「自分の仕事はこれではない」って確信みたいなものを感じたんですよね。それで「私はもう俳優を辞めます」って劇団の皆にも伝えました。とはいえ、その後、なにをするかは決めてはいなくて。そうしたらある先輩から、以前に私が書いた脚本の話をされたんです。
――舞台に立ちながら、劇作もされていた。
高橋 本当に短いものですけど。その時にいろんな人から「脚本が書けるなんてすごい!」って言ってもらえたのがうれしくて。そのうちに皆から「じゃあ、また書けばいい」って背中を押されて、劇団の研究生向けに脚本を書かせてもらったら評判が良くて、本公演もこれでいこう、って話になったんです。
――トントン拍子じゃないですか!
高橋 いや、その後は全然ですよ(笑)。オリジナルの脚本は書き続けていましたが、それで生活ができるわけでもないので、アルバイトもしましたし。
――そのアルバイトがテレビの放送作家さんですよね。またなぜその道に?
高橋 たまたま知り合った人が、舞台関係とテレビの放送作家の両方が所属する事務所にいて「今、あの番組でクイズ作る人を探してるから行ってみたら?」って声をかけてくれたのがきっかけです。それでいろんな番組に関わるようになりました。
――なかなか「訳詞」に繋がらない道のりです(笑)。
高橋 ですよね(笑)。放送作家をしながらオリジナル作品の脚本を書いていたら、あるプロデューサーが「あなたは訳詞に向いてる」と言ってくださって、その人と一緒に仕事をするうちにご縁が広がっていったという感じです。
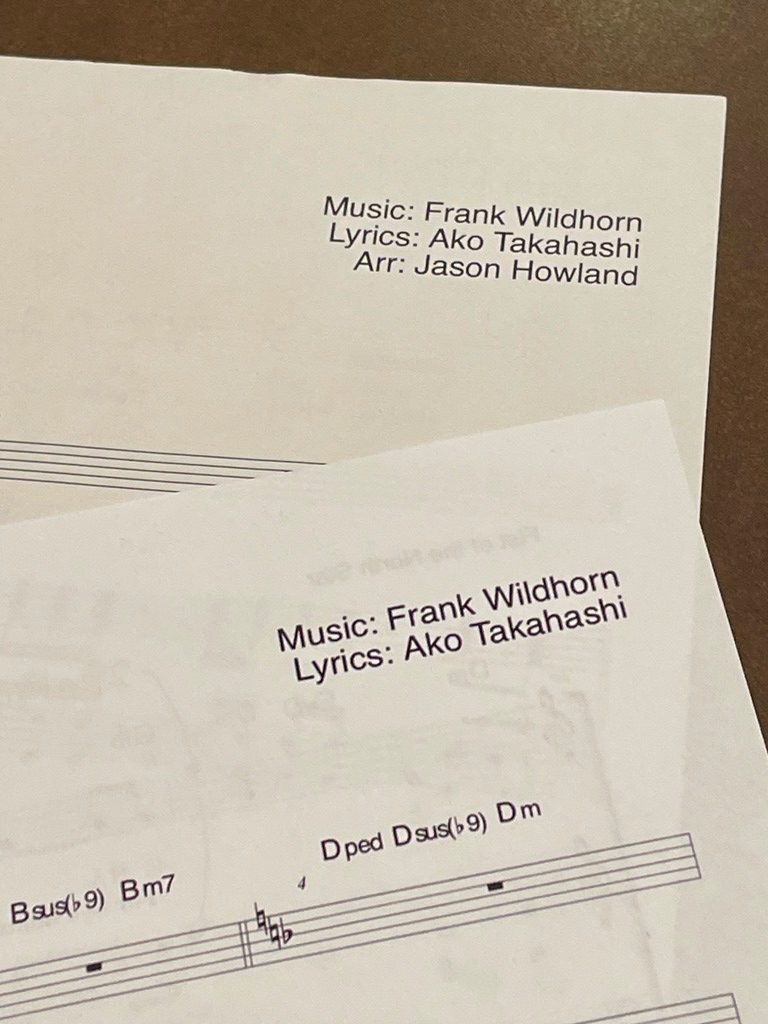
『フィスト・オブ・ノーススター~北斗の拳~』スコアの一部
訳詞の仕事で大切なのは「英語力」より「日本語力」
――あらためて伺いたいのですが、高橋さんは海外で育ったとか、インターナショナルスクールに通っていたとか、英語が常に近くにある環境で過ごされたのですか?
高橋 全然そんなことないんです!大学でも英語を専門的に学んでいたわけではなく、訳詞や翻訳の仕事をするようになってから、あらためてコツコツ勉強しました。
――今のご活躍を考えるととても意外です。師匠的な方もいらっしゃらない?
高橋 劇団時代に、若手の演出家の方が訳詞をするのをそばで見ていたことはありますが、専門の学校に通ったり、師匠のような方にがっちり付いて勉強したという経験はないです。
――ネイティブレベルの方たちしか就けない仕事だと思っていました。
高橋 もちろん、英語の勉強を専門的にやってきた方もいらっしゃいますが、訳詞に関しては、ネイティブレベルでないと無理ってことはないと思います。これは私個人の考えですが、正直、訳詞は英語力より日本語力が肝だと思っています。
――……深い!
高橋 例えば英語独特の言い回しや慣用句、わかりにくいニュアンスなんかはその道のエキスパートに聞けば教えてくれるし、辞書でも調べられるじゃないですか。だけどそれをどういう日本語に置き換えて歌詞をメロディに当てはめていくかっていうのは、やっぱり日本語力なんですよ。
――たしかに!もともと、英語と日本語では1フレーズに入れられる意味の数も違いますよね。お話をうかがっていると、訳詞家さんには英語を日本語表現に置き換える作家性が必要な気がします。
高橋 それはありますね。そもそも英語の歌詞の意味すべてを日本語に訳して音に乗せることは物理的に不可能なので、凝縮しながら削いでいく……って作業が必要になります。その時に、日本語力が高いほど、的確に凝縮して、英語の意味をなるべく削がずに、自然な日本語にすることができます。どういう言葉を組み合わせるかによっても、行間で語れる内容が変わってくるので。
現場での考え方を変えるきっかけになったある出来事
――演出家や音楽監督と訳詞について意見がぶつかることはありますか?
高橋 作品を作っていく上でそういうこともあります。ただ、これは私の場合ですが、基本的に譲れるところは譲ります。というのも、以前、音楽監督さんからのオーダーにどうしても納得がいかなくて、歌詞は直したものの、かなりモヤモヤした作品があったんです。だけど、実際に劇場でオーケストラと歌が合わさったのを聞いたとき、「ああ、これを作りたかったのか」と、ものすごく納得できたんです。演出家や音楽家は私には見えない景色を見てらっしゃるので、それ以来、よっぽど違うと思わない限りは従っています。
――高橋さんの“推し”クリエイターさんってどなたでしょう。
高橋 たくさんいますが、『パレード』でご一緒した演出家の森新太郎さんは意志の力がすさまじいと思いました。どんなことをしても、自分が思う舞台を実現させるんだ!っていう気迫。森さんは歌詞検証会や歌稽古でも、的確なご意見をくださいました。
――『パレード』の冒頭で降った色とりどりで大量の紙吹雪は、今後もミュージカル界で語り継がれていくと思います。そしてもし“推し”俳優さんがいらしたらぜひ!
高橋 今は大貫勇輔さんに魅せられています。私が脚本を担当している『フィスト・オブ・ノーススター』のケンシロウ役で稽古中なのですが、誰よりも考え、準備して、自分の意見を出し、誰よりも動く……本当に素晴らしくて、こういう姿勢をずっと続けてきたから、あれほどのダンサーになったのだなぁと思います。
――即答でした!最後に、高橋さんのお仕事における野望を教えてください。
高橋 今はオリジナル作品に魅力を感じています。もちろん、訳詞や翻訳の仕事も続けていきますが、オリジナル作品のゼロから世界を立ち上げていく感覚って他では味わえないですし、無限の可能性を感じます。日本のオリジナルミュージカルが世界に羽ばたくための礎というか、小さな石の一つにでもなれたら最高にしあわせですね。

【取材note】
日本で上演される大型ミュージカルの約9割は海外作品。私たちが劇場で耳にするほとんどの歌詞は「訳詞」のお仕事を経て紡がれたものです。今回、高橋亜子さんにお話をうかがい、外国語で書かれた原詞の意味を損なわずに日本語歌詞として成立させる難しさを痛感しました。
そして、僭越ではありますが「訳詞」のお仕事はインタビューにおけるライティングの過程と似ているな、との気づきも。相手が語ったことをそのまま書くのではなく、その意味を一旦、自分の中に落とし込み、インタビュイー(対象者)の真意を伝えられる表現で文章にする。まさに“凝縮しながら削いでいく”という点での共通項が見つかり、目からうろこがポタポタ落ちる時間でした。
ふだん、何気なく聴いているミュージカルの日本語歌詞。文字になったものをあらためて読み込んでみると、俳優さんの思いや音楽監督、演出家の意図、さらには訳詞家さんの作家性などさまざまなものが浮き上がってくるかもしれません。
奥深き「訳詞」の世界へようこそ!
取材・文・撮影=上村由紀子