#018 [2024/06.13]
わたしたちの、このごろ
家業も料理も、ここに住んでいる人が誇りに思えるような仕事をやりたいと思っています
浅井瞭太さんRyota Asai


こう語るのは、現在神戸市・長田区で家業であるダクト工事業の見習いとして働きながら、地元の食材を使った弁当屋の開業準備を進める浅井瞭太さん、24歳だ。
2023年、とあるイベントで初めて浅井さんに出会ったとき、彼はまだ大学生だった。
信念を持って自分のやりたいことと向き合う姿を見て、まさにこのインタビューに相応しい存在だと思った私は、彼が社会人になるのを密かに楽しみに待っていた。
代々続く家業を継ぎながら、同じ熱量で自分のやりたいことも諦めない生き方を選んだ浅井さん。
固定概念に縛られず、「できない」を「できる」に変えてきた、そんな彼の物語にせまった。
双子の兄と比べ、劣等感を抱いていた子ども時代。
直感的に「食」に興味が向いていた
幼少期のことを振り返ってもらったとき、彼の口からはじめに出てきたのは「食べるのが好きだった」ということ。
浅井さん:アルバムを見返してみると、何かをしたことよりも味覚の記憶が色濃く残っていることに気がつきました。単純に食べることが好きだったんだと思います。

また、当時知人からもらった山菜図鑑を見るのが大好きだったという浅井さん。
浅井さん:あまり覚えていないのですが、小学5年生の時に粘土で自分の将来の姿を作ろうという授業があって、僕はきのこを採っている自分の姿を作っていました。直感的に食に対する興味のアンテナはそのころから持っていたんだと思います。
その一方で、中学時代までは文武両道で優秀な双子の兄の影に隠れ、自分に自信が持てず、劣等感を抱きながら過ごしていたそう。
浅井さん:なんとなくずっと比べられている気がして苦しかったです。兄とは違うことをして自分の才能を見出したいという思いがありつつ、それがなんなのかを見つけられずに悶々としていました。
突然湧いた外の世界への興味。
料理の楽しさを覚えた留学生活
そんな浅井さんに転機が訪れたのは高校に入学してからのこと。
これまでずっと同じ場所にいた双子の兄とも学校が離れ、一から自分の歩む道を見つめ直した浅井さん。高校一年生の時、のちに母校となる立命館アジア太平洋大学のオープンキャンパスを訪れ、世界への興味が湧いたという。
浅井さん:在校生の半分が海外からの留学生なんですよ。各国から集まった学生たちが一緒に学んでいる姿を見て、漠然とおもしろそう!自分も外の世界を知りたい!と思いました。
そして高校の交換留学制度を利用し、一年間オーストラリアへ留学した浅井さん。しかしそこで何よりも彼の心を動かしたのは料理だった。
浅井さん:留学して半年ほど経ったころ、ハンバーガーショップでアルバイトを始めました。幼いころから直感的に食に興味があったからか、自然とのめり込んでいき、いろいろ教えてもらいながら自分で料理をつくる楽しさを覚えました。

それでも当時の浅井さんは、料理を将来の仕事と結びつけることはなく、いずれは家業を継がなければならないと思っていた。
その後、オープンキャンパスで訪れた大分県の立命館アジア太平洋大学へ入学。彼の考え方は大学時代の多くの出会いによって大きく変化していく。
ボーダーレスな料理屋をつくりたい。
夢破れても途絶えなかった食への想い
浅井さんは、大学で各国から集まった学生たちと学びを深めるなかで、食べられるものに制限のあるムスリムやベジタリアンの友人が数多くできたそう。
食事に制約のある人ない人が混ざり合ってみんなで食卓を囲める場所が少ないと感じた浅井さん。「ないならつくろう!」と、友人とともにボーダーレスな料理屋をつくるため、活動を開始。一年間休学し、資金集めと料理修行、そしてメニュー開発やお店の準備に力を注いだ。
浅井さん:ある程度準備が整い、大学のある別府市に月単位でレンタルできるショップがあったので、そこで小さなお店をスタートさせました。
お店を始めた当初は「おもしろいことをやっている!」と話題を呼び、順調な滑り出しに思えたが、半年を過ぎたころから思い悩むことが増えたそう。
浅井さん:僕たちがいちばん来てほしかったムスリムやベジタリアンの人が全然来てくれなかったんです。のちに気づいたことなのですが、結局妥協点でしかなかったというか。ボーダーレスでどんな人でも食べられるものは作れても、みんなが心から食べたい!と思えるものは作れていなかった。やはり作っている僕たちが当事者でなければ、彼ら彼女らにとって本当によいものは作れない。ヴィーガン料理店・ハラール料理店にはその専門性ゆえの信頼とものづくりの哲学があります。今の自分たちでは力不足だ、と。社会的に絶対必要なコンセプトではあると思うのですが、全てに配慮したものを作ることには限界があるんだと、やってみてひしひしと実感しました。
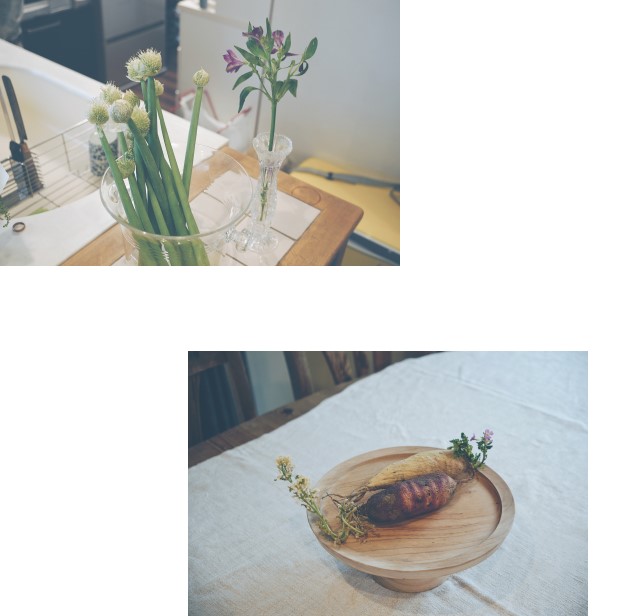
しかし、うまくいかなかったからといって、食への興味を途絶えさせる理由にはならない。料理屋をしながら食材そのものへの探究心が芽生えた浅井さんは、食材の「種」について学んでみたいと、長崎・雲仙にある在来種野菜をあつかう直売所「タネト」の門を叩いた。
浅井さん:今の自分の葛藤を振り払える気がして、直感的に飛び込みました。インターンとして働かせてもらい、料理人として食材の見方を意識する機会をもらいました。
方向性は変わっても、食で世の中をよくしたいという想いは、ボーダーレスな料理屋を目指していたときと何も変わらなかった。
浅井さんは、季節の恵みとその土地の食材を大切にした弁当作りをスタートさせ、少しずつさまざまなイベントに出店するようになり、ますます料理と切り離した人生は考えられなくなっていた。
家業と自分のやりたいことは両立できる。
今は幅が増えたと思っている
高校時代から家業であるダクト工事業を継ぐことを決めていた浅井さん。
家業か料理か、はじめはどちらかひとつに絞らなければいけないと思っていたが、「果たして本当にそうなのだろうか?」と自分自身に問いかけたそう。
浅井さん:よくよく考えてみると、ダクト業を継ぐことも、その土地の恵みを大切にした料理を作ることも、自分の街をよくしたいからという思いは同じなんです。目指すところが同じなら両立できるだろう、と。今は自分の伝えたいことの幅が増えたなと考えるようになりました。

とはいえ、やるからにはどちらも中途半端にはできない。
今は、きちんと事業継承ができるようにダクト工事業の仕事を覚えるタイミングだと割り切っているそう。
浅井さん:イベントなどには変わらず出店しますし、少しずつ自分のお店のことも考えていますが、まずは家業で一人前になれるようにがんばります。ダクトも料理も、いつか地元に住む人が誇りに思ってくれるような、そんな仕事ができるようになりたいです。
私たちはいつも、さまざまな言い訳をつくって「できるかもしれないこと」を「できないこと」に変えてしまっているのかもしれない。その理由は分かっている。「できるかもしれないこと」を「できる」に変えていくのは、時間もエネルギーも必要なことだからだ。
しかし、どちらがいきいきとした生き方だろうか。「自分で道を切り拓いてやる!」と言わんばかりの浅井さんのキラキラとした表情を見ていると、その問いの答えは明白だった。これから私も、前例のないことにチャレンジするとき、できない理由を考えるより、できる理由を考える人間でいたいと心底思うのだった。
STAFF
photo / text : Nana Nose





