【連載】元部員の古民家リノベ 報告 リビングの床編その2【元部員みねてぃのDIYライフ in 吉野】
投稿日:2020年1月15日(水曜日)
こんにちは! 元フェリシモ女子DIY部員のみねてぃです。
古民家リノベーションした時の記録、その21です。

前回はリビングの床をフローリングにするために根太という角材を打ち込み、その間に断熱材を入れました。

今回はフローリングを張っていきます。
まずフローリングといってもさまざまありますよね。ベニヤの上に化粧板を貼ったもの。無垢材のもの。何にするかすごく悩んだのですが、やっぱり無垢材でしょ! と思いそれでも木の種類は何にするか? 最初は硬い木のオークや栗などしたいと思っていて、調べてみたけどやはりお値段は高い。大工さんにオークなどにしたいと相談したら、この地域の気候には合わないんじゃないかという事に。奈良県東吉野村は山の中にあり、谷の間に川が流れその両端に家が立ち並んでいます。ざっくりいうとそんなところです。湿度が高く特殊な気候なので、オークなど硬い木は反りやのちのち材が暴れやすいらしいです。ここらへんでよく使われているのは杉や檜。もともと林業の村なのでそのふたつは吉野杉・吉野檜として日本でもトップクラスのブランドにまでなっています。
「ここで育った木は製品にしてもここになじみやすい」
と大工さんが言っていて妙に納得しました。
ということで、材は檜を選択しました。
たまたまなのですが家の前がフローリングの製造・販売している製材所だったのです。

フローリングを見せてもらい購入。

ここの製材所も杉と檜両方売っていたのですがそれぞれの違いはというと、杉は白太と赤味がある色合いであたりがやわらかく、より温かみがある。その分傷つきやいのがデメリット。杉とくらべて檜は杉よりは硬く色むらが少なく白っぽいです。檜の方が値段は高いです。
傷がつきにくいという面で檜にしました。
無垢材なので節(樹木の成長によって枝がその材中に包みこまれた部分)がはいってくることもあり、まったく入ってないのは値段が高かったり、どれだけ節があるかなどで1等、2等などランクによって値段が変わってきます。あまり節が多く入っていると気持ち悪いと思ってほどほどのランクのものを選びました。
フローリングの断面をみてみるとこうなっています。

両端がさねと呼ばれる部分でデコとボコになっていて差し込んで張っていきます。
端から順に張っていきます。
ひとりがフローリングの長さを切って(動画には写っていませんが)、ひとりが根太に接着剤をつけてあて木を使いながらフローリングを差し込んで、ひとりがフローリングを固定するために穴をあけて釘を打っていきます。

3人がかりでもなかなか大変だし、時間が思ったよりかかります。

一番最後の端っこの始末は大工さんの技が光っていました!
この面積を張るのに3人で約1日半かかりました。

1面フローリングはとても気持ちいい~。
次回は張ったフローリングにコーティングを兼ねて着色していきます。

フェリシモ女子DIY部卒業後は奈良で木工家具工房を開業するためただいま準備中。
インスタグラムでは古民家と工房のリノベーションの様子、また家具などの製作物をあげています。
【インスタグラム】
https://www.instagram.com/wataru830/






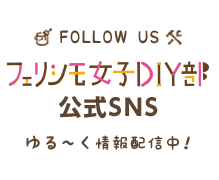
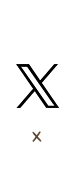





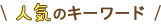

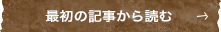
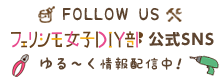









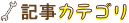






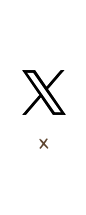




コメントはブログ管理者が公開するまで表示されません。